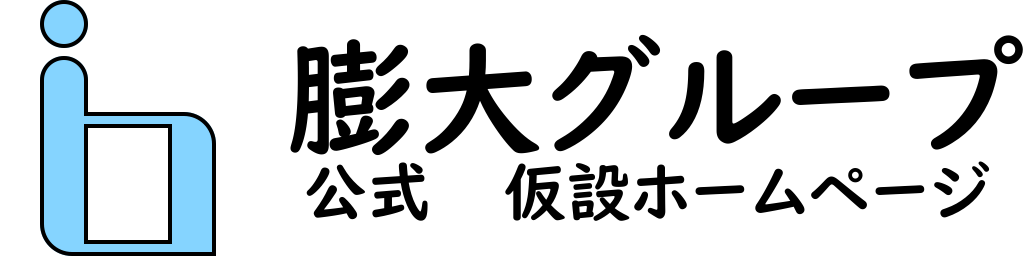※こちらの規則は2025/05/31現在の暫定版です!グループ化完了時までに変更が加わる可能性があります!
以下条文となります。
Contents
第1章 定義
第一条 (定義)
1.「コンテンツ」とは、Wiki、Discordサーバー、SNSアカウント、グループ等、公益のためインターネット上に公開される媒体を指す。
2.「管理人」とは、コンテンツを主として管理する者を指す。
3.「副管理人」とは、管理人を補佐し、コンテンツを管理する者を指す。
4.「管理陣」とは、管理人及び副管理人を指す。
5.「利用者」とは、記事の作成、フォロー、コメント等のコンテンツに対する能動的な参与をする者を指す。
6.「閲覧者」とは、記事の閲覧等のコンテンツに対する非能動的な参与をする者を指す。
7.「外部の者」とは、利用者でない者を指す。
8.「外部組織」とは、膨大グループに所属していない組織を指す。
9.「信用を損なう行為」とは、膨大グループの所属コンテンツ内で厳重注意以上の処分を受けること、もしくはマルウェアの作成などの違法行為を指す。
10.「所属コンテンツ」とは、膨大グループ(以下、本グループ)に所属する全てのコンテンツを指す。
11.「中核コンテンツ」とは、所属コンテンツのうち運営委員会により個別に定められた本グループの中心となるコンテンツを指す。
12.「特別自治コンテンツ」とは、所属コンテンツのうち運営委員会により個別に定められた運営にあたって特殊な取り扱いを受けるコンテンツを指す。
補 足
この他にも規則中で多用される用語について、用語集として参考程度に概要を示す。
- 運営委員会︰毎年4月初旬ごろに選出される3名の運営委員からなる、膨大グループの全体指導組織。全会一致によりその意思を決定する。その内からさらに1名が選出される、運営委員会の代表および膨大グループの最高責任者を運営委員長と呼称する。
- 参考人会議︰利用者のうち特定の条件を満たした参考人が出席する、膨大グループの合議体。多数決によりその意思を決定する。参考人には、権限の高い順に甲種参考人、乙種参考人、丙種参考人がある。
第2章 膨大グループの組織
第一条 (構成)
本グループは下記コンテンツで構成される。
- 中央サイト
- Wiki
- SNSアカウント
- 公式Discordサーバー
- その他運営委員会の承認したもの
第二条 (参考人会議及び運営委員会の設置)
本グループの利用者による合議体として参考人会議を、各コンテンツの管理人及び副管理人の議論の場として管理資格者会議を、本グループの全体指導組織として運営委員会を設置する。参考人会議、管理資格者会議及び運営委員会の選任方法、職務及び権限については第三章に譲る。
第三条 (膨大グループ公式Discordサーバーの設置)
参考人会議、管理資格者会議及び運営委員会の設置場所、そして本グループに関わる諸手続きの場として膨大グループ公式Discordサーバー(以下、公式Discord)を設置する。
第四条 (所属コンテンツの追加)
本グループに新しくコンテンツを所属させる場合は、運営委員会の認可を得なければならない。
第3章 膨大グループの運営
第3-1章 役 職
第一条 (儀礼上の本グループ最高指導者)
初代・2代の膨大なページ数 Wiki* 設立者という立場に配慮して、本グループの「象徴としての代表」は永久的にライキとする。ただし、実際の運営上の特別な権限は一切保持しない。
第二条 (資格の条件と権限)
本グループ運営上の資格者を次の通り定める。
なお、運営委員は参考人と兼任できない。
(1)運営委員
本グループ利用者のうち、選挙を受け当選した者は運営委員となる。
運営委員3名(うち運営委員長1名)によって運営委員会が構成される。
運営委員の資格と条件、選任方法は第三条~第七条で定める。
(2)参考人
本グループ利用者のうち、甲種・乙種・丙種のそれぞれの条件に該当し、審査を受け承認された者は参考人となる。
参考人は参考人会議に参加する。
参考人の資格と条件、選任方法は第八条~第十一条で定める。
(3)管理資格者
所属コンテンツの管理人と中核Wikiの副管理人、および所属コンテンツの副管理人のうち運営委員会の承認を受けた丙種参考人以上の者は、この資格を持つ。ただし、運営委員2名以上、運営委員1名と甲種参考人2名以上、甲種参考人4名以上のいずれかによる明確な拒否があった場合は、与えることができない。
管理資格者は管理資格者会議に参加する。
(4)書 記
甲種参考人から書記長1名、甲種または乙種参考人から一般書記1~3名を選出する。ただし、甲種からの立候補者がいない場合に限り、運営委員会の決議により乙種参考人からも書記長を選出可能とする。任期はないが、参考人会議による不信任決議を受けた場合は解任され、不足分は新規に選出する。
書記は運営委員会の会議や参考人会議・管理資格者会議、その他本グループ内で実施された運営活動の内容を収集し報告する義務を負う。
また、書記長に限り運営委員会室の閲覧権を持ち、参考人会議定例会における報告義務を負う。
(5)一般利用者
全ての利用者は本グループへ参加した時点で一般利用者に分類される。
ただし、運営委員会の決議により拒否された場合は与えられない。1
また、職を失った参考人または運営委員が降格して与えられる(運営委員は乙種・丙種参考人の条件を満たす場合即時再昇格できる)。
第三条 (運営委員の選任)
運営委員は3名とする。運営委員の任期は毎年3月末をもって満了する。
運営委員の選出に際しては甲種・乙種参考人が立候補できる。
立候補終了後、候補者数にかかわらず72時間の投票期間を設け、利用者は各候補者について信任または不信任を投票する。投票終了時点において信任数2が上位の者から3名を選出する。ただし、信任数が負の者は選出されない。票数が同数であるために決定できない場合は、票数が同数であった候補者のみを対象として決選投票を行う。それでも決定できなかった場合は、前任の運営委員長が指名する。
また、信任数が正となった候補者が3名未満であった場合、参考人会議の推薦と決議により不足分を補填する。この際、一度不信任多数となった者も再立候補が可能である。
第四条 (運営委員長)
運営委員会の代表として運営委員から1名運営委員長を選出する。
運営委員長は、その年の運営委員の決定後、運営委員の討議の上、希望者が2名以上の場合は選出投票を、1名の場合は信任投票を経て決定される。
なお、詳細な日付は各年ごとに個別に定める。
第五条 (運営委員会の職務及び権限)
運営委員会は原則として、運営委員および書記長のみが閲覧可能な運営委員会室において、全会一致によってその意思を決定する。また、運営委員会が果たすべき職務は次に掲げるとおりである。
(1)本グループ全体の指揮監督
(2)公式Discordの管理(ロールの付与も含む)
(3)コンテンツの所属許可、剥奪、管理是正命令
(4)外部組織や外部の者からの要請に関する対応
(5)その他重要な、または一般に秘匿されるべき決定事項
(6)その他本規則に定められた運営活動の実行
第七条 (運営委員の罷免および自主退職)
運営委員の罷免は、参考人1名以上からの不信任案が提出され、参考人会議においてそれが可決された場合に限り行える。また、不信任案の決議においてのみ、運営委員は拒否権及び同僚拒否権を行使できない。
また、運営委員は自主的に退職することができる。ただし、これにより本グループの運営に重大な影響を及ぼしかねない場合に限り、参考人会議の決議によりこれを差し止めできる。
運営委員の罷免/退職後の追加選出に関する手続きは第三条を準用する。なお、運営委員長が任期中にその職を失った際は、現職の運営委員から新運営委員長を選出する。
第八条(参考人の条件)
参考人の条件は以下の通りとする。
《丙種参考人》
①本人の同意がある
②甲種参考人2名以上の同意および運営委員1名以上の承認を得る
③過去1ヶ月以内に信用を損なう行為を起こしていない
④公式Discordへの入会から2週間以上が経過している
⑤本グループ内において確認可能な最低限の活動実態がある
《乙種参考人》
①丙種参考人の条件を全て満たしている
②本人の同意がある
③甲種参考人過半数の同意と運営委員会の承認を得る
④1週間に1回以上はグループ内のいずれかの箇所に書き込みをしている
《甲種参考人》
甲種参考人には定数(常時5名)があり、選挙を実施する。以下の条件はあくまでも甲種参考人選挙への立候補条件であることに留意されたい。
①乙種参考人の条件を全て満たしている3
②本人の同意がある
③過去6ヶ月以内に信用を損なう行為を起こしていない
④直近1ヶ月の範囲で、目立った活動休止期間を除き1週間に5回以上はグループ内のいずれかの箇所に書き込みをしている
第九条(甲種参考人選挙)
甲種参考人の任期は6ヶ月である。毎年3月末と9月末をもって任期満了となり、それに伴い甲種参考人選挙を実施する。4
選挙にあたっては、48時間以上の立候補期間、72時間の投票期間、投票終了後1日間の精査期間を設ける。
精査期間終了後、信任数(信任票-不信任票)が上位の者から5名が任命される。
なお、信任数が負の者は任命されず、補欠選挙を実施することにより不足分を補う。この際、一度不信任多数となった者も再立候補が可能である。
甲種参考人選挙への立候補に推薦は必要としない。ただし、上記の条件を満たしていない者については、運営委員会が立候補を拒否する場合がある。
第十条(参考人審査)
乙種・丙種参考人は、3ヶ月に1度、乙種以下の全利用者に対して実施される参考人定期審査により任命される。
参考人定期審査は甲種参考人と運営委員のみが閲覧・発言権を持つ。
また、定期審査時以外でも、必要に応じて特定利用者に対して臨時審査を実施できる。
第十一条(参考人の降格)
参考人が降格される条件は以下の通りである。
(1)信用を損なう行為を行った場合5
(2)甲種参考人の過半数が不承認し、運営委員会に認められた場合(乙種以下のみ)
(3)参考人会議で不承認決議された場合
(4)参考人が自らの意志で降格を要請した場合
第十二条(参考人の権限)
運営委員、各種参考人と一般利用者が持つ権限を以下の表に示す。
また、甲種参考人は以下の権限と義務を持つ。
(1)管理資格者会議への参加
(2)参考人の承認またはその拒否10
(3)Discordのモデレーター権限
1. 投稿の管理 (荒らし対策など)
2. 低速モード設定権と低速のバイパス
3. お知らせチャンネルへの書き込み権限
4. その他緊急時運営委員会から付与される権限
第3-2章 運 営
第十三条(参考人会議の実施)
参考人会議は、毎週1回の定例会と、必要に応じて招集される臨時会からなる。定例会は毎週特定の曜日と時刻から開始する。
運営委員、甲種参考人、書記およびプロジェクト責任者は定例会への出席義務を負う。やむを得ず欠席する場合は、開始前に報告しなければならない。
プロジェクト責任者が欠席した際は、プロジェクト副責任者が代わって出席義務を負う。
なお、運営委員、甲種参考人または書記がそれぞれ1名も出席していない場合、または出席率が著しく低く会議の正常な進行が難しい場合は、定例会を延期することがある。
定例会では以下の議題を取り扱う。
(1)各プロジェクトの進捗に関する報告11
(2)運営委員会室の会議内容報告(書記長が実施。欠席時は省略)
(3)本グループの運営に関する提案など
(4)その他第二条に定める職務の遂行
第十四条(参考人会議の職務)
参考人会議は多数決12によってその意思を決定する。また、参考人会議が果たすべき職務は次に掲げる通りである。
(1)運営委員、甲種参考人などの選挙
(2)本グループに関わる規則の制改定および廃止
(3)その他グループ全体に関わる決定事項
(4)その他本規則に定められた運営活動の実行
第十五条(参考人会議の公開)
参考人会議は原則として一般利用者以上のすべての利用者に対して公開される。
ただし、運営上秘匿が必要と認められた場合、参考人会議の決議により、一般利用者に対してのみ、特定の議題を非公開とすることができる。
これを一般非公開参考人会議と呼称する。なお、一般利用者の閲覧権がなくなる他は通常の参考人会議と同様に進行し、当該議題が終了し次第ただちに解散される。
一般非公開参考人会議が実施された場合でも、書記は当該会議の概略を作成し、一般利用者に対して公表しなければならない。
第十六条 (管理資格者会議の職務及び権限)
管理資格者会議は多数決13によってその意思を決定する。また、管理資格者会議が果たすべき職務は次に掲げる通りである。
(1)管理資格者によってのみ扱われるべき事項の議論と決定
第十七条 (運営委員の拒否権及び同僚拒否権)
運営委員は、各種会議のなした決定に対して拒否権を行使することができる。また、ある運営委員が拒否権を行使した場合、他の運営委員はその行使を拒否することができる。ただしこの同僚拒否権は、同僚拒否権自体に対しては行使できない。
また、自己に関する決定に対しても、拒否権・同僚拒否権は行使できない。
第十八条(プロジェクト)
本グループ内で発生した各種任務のうち、本規則で担当先が定められていないものは、「プロジェクト」として登録することができる。
各プロジェクトでは、特定の利用者(プロジェクト構成員)が集中的に任務にあたる。また、各プロジェクトの最高責任者として「プロジェクト責任者」を、その補佐として「プロジェクト副責任者」をおく。プロジェクト責任者・副責任者は甲種・乙種参考人または運営委員が務める。
プロジェクトの登録は責任者による申請と運営委員会の承認により行われ、任務の終了に伴い解散される。
なお、先述のとおり、進行中の各プロジェクトは参考人会議定例会において進捗状況を報告しなければならない。
第十九条(システム委員会の設置)
次の各号に掲げる委員を構成員とするシステム委員会を設置する。システム委員は甲種・乙種参考人・運営委員から選ばれ、その任免は運営委員会の決議をもって行う。また、各委員は兼務することができる。
(1)システム・情報担当委員
(2)知的財産権担当委員
(3)広報担当委員
(4)コンテンツ審査補助委員
(5)その他運営委員の決議をもって設置する委員
中央サイトと本規則に定める避難所の設置、保有、運用はシステム・情報担当委員が行う。
第二十条(デザイン委員会の設置)
ロゴ、音楽、動画作成等のデザインを行う委員会としてデザイン委員会を設置する。デザイン委員の任免は運営委員会の決議をもって行う。
第二十一条 (特殊技能者)
外国語やIT、政治など、各種分野への造詣が深いと運営委員2名以上に認められた者は特殊技能者に指定する。
平常時は特別な権限を有さないが、運営委員及び参考人会議は特殊技能者に重要事項の決定などを依頼することがある。
第二十二条(公式Discordの機能)
次に掲げる手続きは、公式Discordで行う。これらの手続きに対応するのは運営委員であるが、参考人会議の構成員もやり取りを閲覧することができる。
(1)コンテンツの加入、脱退申請
(2)本グループ内での決定に関する異議申立や要請
(3)本グループに関わる規則に対する欠陥の指摘、問い合わせ
第二十三条(代理人)
年齢や環境のために公式Discordに参加できない手続者は、代理人を立てることができる。ただし、次に掲げる要件を満たさなければならない。また、運営委員1名以上の判断で代理人は無効となる。
(1)手続者が運営委員の閲覧できる場に代理人を立てる旨を表示していること
(2)代理人が、手続者とのやり取りを明確な形で示すこと
第二十四条(所属コンテンツの認定と離脱)
新たなコンテンツが本グループへの加入を希望する場合、当該コンテンツは以下の条件を満たした上で運営委員会の決議による承認を得ることで所属コンテンツに追加される。
(1)条例およびガイドラインの案を運営委員会に提出すること。
(2)管理陣が本規則および膨大グループ規則を充分に理解していること。
(3)コンテンツとして相応しい内容があり、なおかつ公序良俗に反していないこと。
(4)第5章第五条に定める所属コンテンツの条件を満たしていること。
また、所属コンテンツから第5章第六条に定める離脱請求がなされた場合、運営委員会はその内容を審議し離脱の可否を決定する。
第二十五条(所属コンテンツの管理是正命令)
所属コンテンツの運営が適切に行われていない場合、運営委員会は当該コンテンツの管理陣に対して管理是正命令を発することができる。
管理是正命令により、以下の事項を管理陣に対して命令できる。また、管理陣は管理是正命令に必ず従わなければならない。
(1)副管理人の解任
(2)条例・ガイドラインの修正
(3)ページの作成・修正・削除
(4)管理人の交代
(5)その他運営に関わる事柄
第二十六条(所属コンテンツの脱退命令)
正当な理由がある場合、運営委員会の決議により、所属コンテンツについて膨大グループからの脱退を命じることができる。
第二十七条(会議録の開示)
利用者からの要請があった場合、管理資格者会議及び運営委員会会議、その他本グループ内で実施された会議の会議録は、当該会議の参加者による決議の上適切な形で開示されなければならない。(参考人会議の公開方法は第十四条に定める。)
ただし、個人情報等の守秘しなければいけない内容に関しては、運営委員会の決議をもって守秘することを決定した上で、書記により守秘部分の概略を示すことで代える。
第二十八条(異議申し立て)
利用者は本グループ内のすべての決定事項に対して、発表から3日以内であれば自由に異議申し立てができる。異議申し立てがあった場合、当該決定事項の会議参加者による決議の上、再投票など適切な措置を講じなければならない。
ただし、一度異議申し立てがあり再決定された事柄に対して、再度異議申し立てをすることはできない。
第4章 所属コンテンツの組織
第一条 (各コンテンツの組織構成)
各コンテンツには原則として管理人を1名、またその補佐として副管理人を1名以上おく。
各コンテンツの利用しているサービスが規定した管理者や、それに準ずる最高権限保持者などは自動的に管理人として認定される。事情があって、管理人を容易に同定できない場合は届け出なければいけない。
また、次の者は、副管理人とみなす。
(1)システム上の都合で、管理人のアカウントやパスワードを共有して副管理人の代替となっている者
(2)システム上の都合で副管理人を設置できず、権限上は他のコンテンツ利用者と同列であるが、管理人から運営上の権限を認められ、その旨を表示している者
原則として管理人は、公式Discordに参加しなければならない。ただし、事情があって不可能な場合は適切な連絡先の提示をもってそれに代えることができる。
第二条 (管理人の権限)
管理人は各コンテンツの代表者として以下の権限と責任を持つ。また、特記しない限り副管理人の持つ権限は管理人も持つ。
(1)各コンテンツの使用するサービスにおいて定められた権限を行使すること。
(2)各コンテンツの利用者の代表として運営の責任を負うこと。
(3)副管理人を任命すること。
(4)管理資格者として管理資格者会議に参加すること。
第三条 (副管理人の選定方法)
副管理人は、特別自治コンテンツを除き、原則として利用者による選挙で選任する。
選挙の実施方法は各コンテンツ条例により定める。
第四条 (副管理人の条件)
副管理人は以下のすべての条件を満たした者でなければならない。
(1)当該コンテンツにおいて継続的かつ積極的に活動していること。
(2)当該コンテンツの利用者となってから60日以上が経過していること。
(3)過去に当該コンテンツにおいて30日以上の有期規制を受けていないこと。
(4)冷静かつ丁寧な言動や行動ができ、利用者の代表となるに相応しい者であること。
第五条 (副管理人の権限)
副管理人は特別に以下の権限と責任を持つ。
(1)各コンテンツの使用するサービスにおいて定められた権限を行使すること。
(2)各コンテンツの利用者の代表として議論を進行すること。
(3)各コンテンツの利用者を監視し平和を保つこと。
(4)各コンテンツの運営において管理人に次いで責任を負うこと。
第六条 (副管理人の罷免請求)
各コンテンツの利用者は、副管理人の罷免を請求する権利を持つ。
罷免請求がなされた場合、以下の手順により弾劾の投票を行う。
① 当該コンテンツの利用者で48時間投票を実施する。
② ①で賛成多数だった場合、本グループの参考人会議で投票を実施する。ただし、請求者および被請求者は投票の権利をもたない。
③ ②で可決された場合、当該コンテンツの管理人が被請求者の権限を解除する。
第七条 (管理人の意思による罷免)
管理人は、利用者による投票を経ず、副管理人の解任を本グループに直接請求できる。
その後の扱いは第五条②以降と同様のものとする。
第八条 (異議申し立て)
副管理人の任命・解任に正当な理由が認められない場合、任命・解任手続きの終了から2日以内であれば利用者は異議申し立てができる。
異議申し立てがなされた場合、本グループの参考人会議で再投票の可否を議論しなければならないものとする。
第九条 (管理人の辞職)
各コンテンツの管理人は、運営委員2名以上の了承を得ることで辞職できる。この際、現職の管理人は自らの後任を推薦できる。
利用者間で被推薦者に対する信任投票を48時間行い、参考人会議と運営委員会に認定された後、管理人の交代ができる。
第十条 (副管理人失踪時の取り扱い)
各コンテンツの副管理人と2ヶ月以上連絡が取れない場合、当該副管理人を解任する。
これにより副管理人が存在しなくなる場合、新規に選出する。
第十一条 (管理人失踪時の取り扱い)
各コンテンツの管理人と2ヶ月以上連絡がとれない場合、副管理人の中から協議で選ばれた1人を暫定管理人とする。
システム上の管理人権限がないことにより不都合が生じ運営委員2名以上に了承を取った場合、もしくは暫定管理人就任から半年が経過した場合は暫定管理人が管理人権限の引き継ぎを行うことができる。この場合、暫定管理人が正式に管理人となる。
なお、副管理人が不在の場合は暫定管理人を48時間以上の投票によって決定する。以降の取り扱いは同一とする。
第十二条 (管理権限引き継ぎ不能時の取り扱い)
上記第十条または第十一条を適用する際、Wikiサービスなどの都合により管理権限の引き継ぎが行えない場合は別サイトへのコンテンツの移転を行う。
引き継ぎを行う際は、原則として規則・条例などの変更を行わない。
第5章 所属コンテンツの運営
第一条 (所属コンテンツの自治権)
各コンテンツは、各コンテンツ条例に規定された範囲内で自治権を行使し、運営行為を行える。
利用者は運営行為が適当でないと判断した場合、異議申立を行うことができる。また参考人会議は決議によって是正勧告をすることができる。
第二条 (条例の制定)
各所属コンテンツは条例を定めなければならない。
条例には、当該コンテンツにおけるページの取り扱い、副管理人の選定方法、会議の進行方法等、本規則に定められていない運営行為の取り扱いや、各コンテンツの状況に応じたルールを記すものとする。ただし、第三条に定める場合を除き、本規則ないしは各コンテンツの利用するサービスの利用規約に違反する条項の記載はできない。
条例の制改定案は、各コンテンツで可決されたのち、運営委員会に提出し審査を受けなければならない。運営委員会に修正を命令された場合、各コンテンツはそれに従う義務がある。審査のうえ承認を得たあと、1日以上経過後に公布・施行できる。
第三条 (特別自治コンテンツ)
本グループ特有の文化の継承と発展、もしくは本グループ運営上の利便のため、一部の所属コンテンツは参考人会議を経て特別自治コンテンツに指定される。特別自治コンテンツは本規則を部分的に無視した条例を制定できる。ただしこの場合であっても審査は受けなければならない。
また、前述の目的に反した自治権の濫用が認められた場合、運営委員会は当該コンテンツの特別自治指定を解除できる。
第四条 (ガイドライン)
一般利用者に広く規則の周知を図るため、各コンテンツは、本規則と当該コンテンツ条例を平易に簡略化したものとしてガイドラインを制定しなければならない。ガイドラインは条例と同時に案を提出し審査を受け制改定される。なお、本規則の改定時には、運営委員会は全所属コンテンツに一括で改定の命令を出すことができる。
第五条 (所属コンテンツの条件)
各コンテンツは常に以下の条件を満たしていなければならない。
(1)運営行為が存在していること。各コンテンツは管理陣か、またはコミュニティによって承認された管理陣に準ずる者によって各コンテンツの維持または改善をする行為がなされているか、そのような行為が可能な状態でなければならない。
(2)利用実態が存在していること。各コンテンツは管理陣でない利用者が現存していなければならない。ただしシステム上の事情で利用者の能動的な反応が期待しにくいものについては、運営委員会は状況に応じて考慮する。
(3)条例およびガイドラインをコンテンツ上の分かりやすい位置に掲示していること。
第六条 (グループからの離脱)
正当な理由がある場合、各コンテンツの管理陣は本グループからの離脱を利用者に提案することができる。
提案がなされた後は48時間以上の利用者投票を実施し、過半数が賛成した場合は運営委員会に離脱の請求を行うことができる。
第七条 (バックアップ送信義務)
各コンテンツの管理人は、最低1年に1回以上、当該コンテンツのバックアップデータを運営委員会に提供しなければならない。
ただし、バックアップデータの取得が困難なコンテンツについては審議の上対応する。
第八条 (規則の継続適用)
各コンテンツは、グループからの離脱・追放後、新たな規則・ルールを制定するまで当規則・条例を臨時で継続適用することができる。
第6章 禁止行為と処罰
第一条(禁止行為)
第四条に掲げる行為は、所属コンテンツ内でしてはならない。
ただし、所属コンテンツにおける禁止行為は各コンテンツ条例において別途定める。
また、原則として第四条に掲げられた行為以外の行為を根拠として処罰を行うことはできない。ただし、明らかな緊急性がある場合に限り運営委員の決議によって特例で処罰を行うことができる。
第二条(処罰)
実際の処罰に関しては、各コンテンツの事情に配慮して、各々の管理陣の定めるところに拠るとする。ただし、処罰の内容は利用者が常に閲覧できるような状況に置かれねばならない。
また、処罰の内容に異議がある場合は公式Discord及び他の連絡手段によって異議申立ができるようにしなければならない。
第三条(細則)
1. あるコンテンツにおいてなされた禁止行為に対しては、同コンテンツ内でのみ処罰しなければならない。ただし運営委員1名以上が、禁止行為の内容が悪質であり、複数コンテンツに跨がって害を与える可能性があると認定した場合は、ある禁止行為に対する処罰を本グループ内の別コンテンツに同様に適用できる。
2. 次の者は正犯であり、禁止行為を実際に行った者と同様の処罰とする。
(1)他人をそそのかして禁止行為を行わせた者
(2)集団で禁止行為を行うことを謀議した者のうち、実際は禁止行為を行わなかった者
3. 次の者は従犯であり、禁止行為を実際に行った者より適宜処罰の程度を下げるものとする。
(1)明らかに脅迫されて禁止行為を行ったことを立証できる者
4. 明らかに悪意なくして行ったと認定できる行為に関しては処罰の程度を下げてもよい。
第四条(禁止行為の一覧)
赤色を付けられた行為は特に本グループに与える不利益が大きく、重い処罰が期待される。
| 行為名 | 行為の内容 |
|---|---|
| 健全な運営を妨げる行為 | |
| 議事妨害 | スパム等でコンテンツ上の公式な会議を妨げること |
| 基本構成要素の削除 | 条例やガイドラインを掲示するページ、会議に用いる掲示板等の運営に不可欠なページを無断で削除すること |
| 不正投票 | 投票内容を自身が有利になるように、または別の目的で改ざんし、また複数投票を行うこと |
| 運営システム妨害 | 運営システムに必要なページやチャンネル等を削除または機能不全にすること |
| なりすまし | 他人のアカウント名、固定ハンドル等を名乗り、本人と誤認させること |
| 名称偽装 | 新規のアカウント名、固定ハンドル等を名乗り、別人であると装うこと |
| 規制抜け | 個人識別手段の変更等を利用して、投稿もしくは閲覧禁止の処罰を回避すること |
| 管理陣の詐称 | 管理陣を詐称して運営行為を行うこと |
| 管理陣の命令の無視 | 管理陣の明示的な複数回に渡る命令を無視すること |
| 条例及びガイドラインの不遵守 | 各コンテンツにおいて独自に定める条例やガイドラインにおけるルールに従わないこと |
| 禁止行為実行の予告 | 禁止行為を行うことを予告すること14 |
| 職務怠慢(運営委員) | 特段の事情がないにもかかわらず、運営委員全員が、運営委員として果たすべき職務を、その必要性の発生から2週間が経過しても処理しないこと |
| 職務怠慢(管理陣) | 特段の事情がないにもかからわず、管理陣全員が、管理陣として緊急性の高い職務を、その必要性の発生から2週間が経過しても処理しないこと |
| 規則の欠陥報告の怠慢 | 利用者が、規則の欠陥を認識したにもかかわらず、それを直ちに報告しないこと |
| 抜け穴行為 | 規則及び各コンテンツ条例においてしてはいけないと規定された内容に抵触しないように、故意に調整を行うこと |
| 外患誘致 | 悪意をもって、外部からコンテンツ運営を阻害しうるような人物もしくは組織を所属コンテンツに誘導すること |
| 欺瞞行為 | 自己の利益のために、もしくは娯楽として、運営上の権限をもつ人物を騙して何らかの行為を行わせること |
| 不正操作 | サービスを濫用し、またマルウェア等を用いてコンテンツの運営に不正介入し、もしくは利用者に害を与えるような変更を行うこと |
| 利用者及び閲覧者に不利益を与える行為 | |
| 無断削除 | 限度15を超えて他人の投稿を無断で削除すること |
| 危険な内容の投稿 | マルウェアの掲載等のセキュリティ上問題があり、利用者に害を与える可能性がある内容、もしくは明らかに違法である内容を含む投稿を行うこと |
| 局外者に関わる行為 | |
| 詐称を伴う問題行為 | グループもしくは所属コンテンツの公式な行動であるかのように装って、外部の者もしくは外部組織に対して問題行為を働くこと |
| サービス規約違反 | 利用しているサービスの示す規約に違反する行為を行うこと |
第7章 責任の所在
第一条 (外部の者及び外部組織との紛争の責任)
各コンテンツと外部の者または外部組織の間の争いにおいて発生した責任は本グループに帰属する。
第二条 (内部の紛争の責任)
各コンテンツ利用者間あるいは各コンテンツ利用者と外部の者または外部組織の間で発生した争いについて本グループは一切責任を負わない。
ただし、それにより本グループ全体および外部組織の秩序を著しく乱した場合、規制などの処置をとる。
また、サービスの終了により各コンテンツが予告なく閉鎖した場合でも本グループは責任を負わない。
第三条 (外部の者及び外部組織に対しての責任)
外部の者が各コンテンツに記述された内容によって心理的ないしは物理的に影響を受けた場合、本グループがその責任を負う。
また、外部組織が各コンテンツに記述された内容によって評判の低下や荒らしなどの影響を受けた場合、本グループがその責任を負う。
更に、各コンテンツにおいて、第三者の攻撃やインターネットの脆弱性などにより個人情報が意図せず漏洩する場合があるが、その場合本グループは責任を負わない。ただし、運営委員に問題があった場合はこの限りでない。
第8章 著作権関連
第一条 (各コンテンツの著作権の帰属)
各コンテンツの編集者が作成し、各コンテンツに投稿されたすべての文章および画像・動画・音声などの著作物の著作権は本グループと編集者双方に帰属する。
第二条 (無断引用の削除要請)
各コンテンツに著作権が帰属する著作物を外部の者または外部組織が無断引用した場合、削除の要請を出す権利がある。
第三条 (外部著作物の引用)
外部の者および外部組織に著作権が帰属する著作物を各コンテンツにおいて使用する場合、権利保持者に必ず許可を得なければならない。
ただし、出典元を注釈にて表示した上での引用、及びクリエイティブ・コモンズなどに定められた再使用可能なコンテンツの使用はこの限りではない。
なお、文体の変更や画像の加工など、改変があった場合にもこの条項は適用される。
第四条 (不明・曖昧な場合の取り扱い)
権利関係が不明あるいは曖昧な著作物については各コンテンツ条例において個別に定める。
第五条 (外部の者からの削除要請)
各コンテンツにおいて外部の者及び外部組織の著作権もしくは著作者人格権を侵害していた場合、権利保持者は運営委員に対して削除要請を行うことができる。
削除要請は本グループの定めるお問い合わせフォーム、もしくは運営委員宛のEメールで行うことができる。
正当な理由、及び正式な方法で削除要請を受けた場合、運営委員及び各コンテンツ管理陣は3日以内に対応する必要がある。
第9章 プライバシーポリシー
第一条(初めに)
当個人情報保護方針(プライバシーポリシー、以下「本ポリシー」という)は、本グループの所属コンテンツ内において、管理陣が利用者、及び、その周囲の人物の個人情報に対する不正使用および不正流布を行わないことを示し、本グループの所属コンテンツ内での同利用者の個人情報取り扱いに関するガイドラインとして作成されたものである。
第二条(定義)
(1)個人情報
本ポリシーに置いて「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、および次の各号のいずれかに該当するものを指す。
イ. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等1617に記載され、もしくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く)をいう。以下同じ。))により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
ロ. 個人識別符号が含まれるもの
(2)個人識別符号
本ポリシーにおいて、「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号、その他の部号のうち、政令で定めるものを指す。
イ. 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
ロ. 個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、「運転免許証」「保険証」「マイナンバーカード」など公式発行書類に記載される個人識別番号や、企業などの商品販売時に作成、添付される書類に記載される購入者識別番号など、特定の利用者もしくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3)本 人
本ポリシーにおいて「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人を指す。
第三条(利用者の取り扱い)
【管理陣】
(1)流 布
各コンテンツにおいて、管理陣は、絶対に無断、及び不必要な個人情報の流布を行わず、それを示唆する文章の投稿を行わない。ただし、未成年者・成年被後見人の法定代理人又は本人から委任を受けた代理人による正当な開示請求を受けた場合は、個人情報を開示する場合がある。
(2)収 集
各コンテンツにおいて、管理陣は、絶対に不必要な個人情報の収集を行わない。ただし、一般利用者から副管理人への格上げ時など、特定の本人のみに伝達する必要が発生した場合のみ、その本人の通信に関する個人情報を収集する場合がある。
(3)利 用
各コンテンツにおいて、管理陣は、絶対に不必要な個人情報の利用は行わない。ただし、上記の状況を含める特殊な状況下に限り、特定の本人のみに伝達する必要が発生した場合のみ、その本人の通信に関する個人情報を利用する場合がある。
【一般利用者】
(1)流 布
本人の生命、又は社会的尊厳の危機などの特殊な状況下にさらされた場合などの特殊な状況下を除き、他人の個人情報を無断、及び不必要に流布することを絶対に禁じる。
(2)自己開示
本グループ所属コンテンツにおいて、本人が自らの個人情報を開示することは禁止しない。しかし、自らが行った個人情報の開示により発生した出来事に対し、本グループは一切その責任を負わない。
第三条(個人情報の第三者提供)
本ポリシーに基づき、各コンテンツは、以下の場合を除き同意を得ず第三者に情報を提供及び開示することは絶対に行わない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第四条(本ポリシーの改変)
本ポリシーの改変は以下の状態が認められた場合のみ許可され、変更後のプライバシーポリシーは、プライバシーポリシーの変更を適用した瞬間からその効力を生じるものとする。
(1)本ポリシーが当時の時代において個人情報の保護が行えないと認められた場合。
(2)改変後においても、その目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合。
(3)本グループ全体への大規模な改変により本ポリシーの目的維持が困難になった場合。
また、本ポリシーは法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、一般利用者に通知することなく変更できるものとする。
第五条(処罰)
本ポリシーに違反した場合の処罰は、第6章において定める。
第六条(お問い合わせ窓口)
本ポリシーに関するお問い合わせは下記の窓口にまでお願い申し上げます。
- 膨大グループDiscordサーバー お問い合わせチャンネル
(現在諸事情によりリンク非公開) - 膨大グループ中央サイト お問い合わせフォーム
(現在作成中、当面は当サイトのお問い合わせフォームよりお願いします) - 膨大グループ 運営委員宛メール
(現在存在しません)
第10章 緊急時の取り扱い
第一条(グループに関わる運営行為を行う場所の避難)
公式Discordが何らかの理由で長期的、もしくは永久的に利用不可能になった場合は、次に掲げる各号の順を優先順位として、避難を行う。ただし、避難先は運営委員全員及び運営委員を除いた参考人の三分の二以上に出席が可能なものである上で、運営委員の決議による事前承認または事後承認が行わなければならない。
(1)Discordの別のサーバー
(2)X(旧Twitter)のDMグループ
(3)その他、アカウント登録を要求し、閉鎖的な環境でグループ会議を構築することが可能なSNSサービスにおけるグループ
第二条(中央サイトの避難)
中央サイトが何らかの理由で長期的、もしくは永久的に利用不可能になった場合に備えて、仮避難所としてアットウィキもしくは運営委員の決議によって指定される、オープンアクセスであって、セキュリティ面で問題がなく、相当の量の投稿を行うことができるサービスに中央サイトのミラーを作らねばならない。
また、中央サイトが利用不能となってから30日以内に、運営委員の決議をもって決められたサービスに中央サイトの機能を移管する。
第三条(所属コンテンツの避難所)
所属コンテンツは、次に掲げる要件をすべて満たせば、利用不可能時にその避難所を継承先として用いることができる。満たしていない場合、別途コンテンツ加入申請をしなければならない。
(1)避難所として用いるサービス名を利用者に対して明示していること18
(2)避難先の管理人が、避難前の管理人と同一人物であることの確認手段があること
第四条 (避難所)
各コンテンツにおいて、大規模な荒らしやシステムエラー、削除などの不可抗力により閲覧・書き込みが不可能になった場合、膨大グループ公式Discordを避難所として情報共有を行う。
Discordにアクセスできない利用者の避難所は中央サイトで表示する。
公式Discordも閲覧・書き込みが不可能になった場合、公式X(旧Twitter)アカウント、中央サイトで避難所を表示する。
第五条 (規則の保管)
緊急時のため、公式Discordおよび公式のGoogleドライブには当規則の複製を保存する。
第六条 (管理人の緊急大権)
管理人は、非常時に限り緊急大権を行使できる。
緊急大権の行使によって、各コンテンツ条例に定めた手順を無視して運営活動が可能になる。
緊急大権の行使後は運営委員に内容と正当な理由を報告しなければならない。
なお、運営委員2名以上の判断、または参考人会議によって差し止めおよび事後撤回命令ができる。事後撤回命令があった場合は責任を持って実行者が復元する。
第七条 (運営委員会の緊急大権)
運営委員会は、非常時に限り緊急大権を行使できる。
緊急大権の行使によって、本規則に定めた手順を無視して運営活動が可能になる。
緊急大権の行使後は参考人会議に内容と正当な理由を報告しなければならない。
なお、参考人会議によって差し止めおよび事後撤回命令ができる。事後撤回命令があった場合は責任を持って復元する。
また、運営委員会が緊急大権の濫用などの不適切な発動を行った場合は、その責任の追及を免れない。
- その場合でも本規則に規定された利用者としての権利と義務は持つが、参考人会議の閲覧や参考人への昇格はできない ↩︎
- 信任票数-不信任票数 ↩︎
- 乙種の条件を満たしていれば、丙種参考人からの立候補も可能である ↩︎
- 3月末は、より上位の役職である運営委員選挙を先に実施するのが望ましい ↩︎
- 即時一般利用者に降格。一定期間が経過し参考人条件をクリアしても自動再昇格はしない ↩︎
- ただし一般非公開参考人会議は× ↩︎
- ただし管理資格者は〇 ↩︎
- 同左 ↩︎
- 管理資格者の一般利用者は存在しない ↩︎
- 上記第四条・第五条 ↩︎
- プロジェクトについては第十八条に記載 ↩︎
- 過半数の賛成で可決。同数の場合は再議論の上、それでも決定しなければ運営委員会が最終決定権を有する ↩︎
- 過半数の賛成で可決。同数の場合は再議論の上、それでも決定しなければ運営委員会が最終決定権を有する ↩︎
- 冗談や濫用の可能性を考慮して、管理陣は慎重に判断すること ↩︎
- 管理陣の運営行為における削除、誤字訂正、個人情報もしくはマルウェア等の拡散を防ぐための緊急削除。または運営委員の決議による承認(この場合、事後承認を許可する。) ↩︎
- 住所、所属組織名、IPアドレス、メールアドレス、電話番号などを言う ↩︎
- 文書、図画もしくは電磁的記録で作られる記録を呼ぶ。以下同じ。なお「電磁的記録」とは、電磁的方式、すなわち電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。 ↩︎
- 必ずしも事前開設の必要はない。 ↩︎